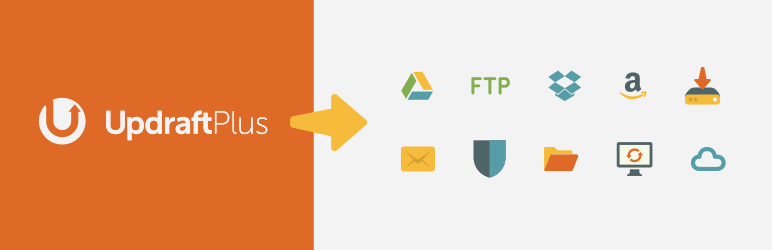WordPressサイトを運営していると、いつ何が起こるか分からないものです。ハッキング、サーバー障害、うっかりミス…。そんなとき、「あのときバックアップしておけば」と後悔したことはありませんか。
実は、WordPressのバックアップは思っているより簡単にできます。今回ご紹介する「UpdraftPlus」は、クリック一つでサイト全体をバックアップし、Google DriveやDropboxなどのクラウドサービスに自動保存してくれる優秀なプラグインです。
無料版でも十分な機能を持ち、世界中で300万以上のサイトに導入されています。設定も復元も管理画面だけで完結するので、初心者でも安心して使えますよ。
何ができるの?UpdraftPlusってこんなプラグイン
1. まるごとバックアップが1クリックでできちゃう
UpdraftPlusの最大の魅力は、サイト全体のバックアップがとても簡単なことです。「今すぐバックアップ」ボタンを押すだけで、以下のデータがまるごと保存されます。
| バックアップ対象 | 内容 |
|---|---|
| データベース | 記事、固定ページ、コメント、設定情報 |
| プラグイン | インストール済みのプラグインファイル |
| テーマ | 使用中・未使用のテーマファイル |
| アップロード | 画像や動画などのメディアファイル |
| その他 | wp-contentフォルダ内の追加ファイル |
通常のレンタルサーバーでは、バックアップがあっても復元が複雑だったり、一部のデータしか対応していなかったりします。しかし、UpdraftPlusなら「ファイル」と「データベース」を分けて管理し、必要な部分だけを復元することもできるんです。
たとえば、新しいプラグインを試して不具合が出た場合。プラグインフォルダだけを復元すれば、記事データはそのまま残して元の状態に戻せます。これって、かなり便利だと思いませんか。
2. クラウドに自動保存で安心感がレベルアップ
サーバー内だけにバックアップを保存していると、サーバー自体に問題が起きたときにバックアップも一緒に失われてしまいます。UpdraftPlusなら、以下のクラウドサービスと連携できるので、この心配がありません。
| クラウドサービス | 無料容量 | 特徴 |
|---|---|---|
| Google Drive | 15GB | Googleアカウントがあればすぐ利用可能 |
| Dropbox | 2GB | ファイル同期が高速で安定している |
| OneDrive | 5GB | Microsoft製品との連携が良い |
| Amazon S3 | 従量課金 | 大容量サイト向け、高い信頼性 |
実は、多くの企業でも同じような「オフサイトバックアップ」が推奨されています。つまり、UpdraftPlusを使えば企業レベルのバックアップ戦略を個人サイトでも実現できるということです。
ここで注意したいのは、クラウド容量の制限です。画像や動画が多いサイトでは、Google Driveの15GBでも足りなくなる可能性があります。ただし、古いバックアップを自動削除する設定もあるので、うまく運用すれば無料範囲内でも十分対応できますよ。
3. 復元も簡単!管理画面だけで元通りに
バックアップを取るのは簡単でも、いざ復元となると複雑な作業が必要なプラグインもあります。しかし、UpdraftPlusの復元は本当にシンプル。管理画面の「既存のバックアップ」から該当するバックアップを選び、「復元」ボタンを押すだけです。
復元時には以下の選択肢があります:
- 完全復元:サイト全体を指定した日時の状態に戻す
- 部分復元:プラグインだけ、テーマだけなど特定の要素のみ復元
- データベースのみ:記事内容や設定だけを復元
復元作業中は、サイトが一時的にアクセスできなくなりますが、通常は数分程度で完了します。万が一復元に失敗しても、元のバックアップは残っているので、何度でもやり直せるのも安心ポイントです。
初心者でも大丈夫!UpdraftPlusのインストールから初回設定まで
1. プラグインをインストールして有効化する手順
UpdraftPlusのインストールは、他のWordPressプラグインと同じ流れです。まず、管理画面の「プラグイン」→「新規追加」から「UpdraftPlus」で検索しましょう。
検索結果に「UpdraftPlus WordPress Backup Plugin」が表示されたら、「今すぐインストール」をクリック。インストールが完了したら「有効化」ボタンを押します。
有効化が成功すると、管理画面の左メニューに「UpdraftPlus バックアップ」という項目が追加されます。ここがUpdraftPlusの操作画面になるので、覚えておいてくださいね。
インストール直後でも、基本的なバックアップ機能はすぐに使えます。ただし、より安全で便利に使うためには、いくつかの設定を調整することをおすすめします。
2. 初回バックアップで動作確認をしてみよう
設定を変更する前に、まずは動作確認として手動バックアップを実行してみましょう。UpdraftPlus画面の「今すぐバックアップ」ボタンをクリックすると、バックアップの種類を選択する画面が表示されます。
初回は「データベース」「プラグイン」「テーマ」「アップロード」「その他」すべてにチェックを入れて実行してください。バックアップの実行時間は、サイトの規模によって異なりますが、一般的なブログサイトなら数分程度で完了します。
バックアップが成功すると、「既存のバックアップ」セクションにファイルが表示されます。ここで重要なのは、各ファイルのサイズと日時を確認すること。明らかにサイズが小さすぎる場合は、何らかのエラーが発生している可能性があります。
実は、この初回バックアップでトラブルが発生することも少なくありません。エラーメッセージが表示された場合は、サーバーのメモリ不足やタイムアウトが原因の可能性があります。
3. ツアーガイドは見る?スキップする?
UpdraftPlusを初めて開くと、機能を説明するツアーガイドが表示されることがあります。「Skip tour」でスキップもできますが、5分程度で終わるので一度は見ておくことをおすすめします。
ツアーガイドでは以下の内容が解説されます:
- バックアップボタンの場所と使い方
- 設定画面の基本的な見方
- クラウド連携の概要
- 復元方法の基本
特に、「設定」タブと「バックアップ/復元」タブの違いは重要です。設定タブでは自動バックアップの頻度やクラウド連携を設定し、バックアップ/復元タブでは実際のバックアップ作業や復元作業を行います。
ただし、ツアーガイドは英語表示の場合があります。日本語に慣れている方は、実際に操作しながら覚える方が理解しやすいかもしれませんね。
クラウド連携で安全性アップ!保存先の設定方法
1. Google Driveと連携してみよう
Google Driveとの連携は、Googleアカウントを持っていれば数クリックで完了します。UpdraftPlusの「設定」タブを開き、「リモートストレージを選択」で「Google Drive」を選択してください。
設定手順は以下の通りです:
- 「Google Drive」を選択して「変更を保存」
- 「Googleで認証」ボタンをクリック
- Googleのログイン画面でアカウントを選択
- UpdraftPlusに権限を与えることを承認
- 認証コードをUpdraftPlusの画面に入力
認証が完了すると、Google Driveに「UpdraftPlus」フォルダが自動作成されます。今後のバックアップファイルは、すべてこのフォルダ内に保存されるようになります。
ここで注意したいのは、Google Driveの容量制限です。無料版では15GBまでなので、大きなサイトでは定期的に古いバックアップを削除する必要があります。ただし、後述する自動削除設定を使えば、この作業も自動化できますよ。
2. Dropboxでもカンタン設定
Dropboxとの連携も、Google Driveと同様にシンプルです。ただし、Dropboxは無料容量が2GBと少ないため、小規模サイト向けと考えた方が良いでしょう。
Dropbox連携の流れ:
- 「設定」タブで「Dropbox」を選択
- 「Dropboxで認証」ボタンをクリック
- Dropboxのログイン画面でサインイン
- アプリの接続許可を承認
- 設定保存で連携完了
Dropboxの利点は、ファイル同期の速度が速いことです。バックアップファイルの生成から、クラウドへのアップロードまでの時間が短縮されます。
また、Dropboxには「バージョン履歴」機能があり、誤ってファイルを削除したり上書きしたりしても、30日間(無料版)は元に戻せます。これは、万が一のときに心強い機能ですね。
3. その他のクラウドサービスとの連携方法
UpdraftPlusは、Google DriveやDropbox以外にも多くのクラウドサービスに対応しています。特に、大容量サイトや本格的な運用を考えている場合は、以下のサービスも検討してみてください。
| サービス名 | 特徴 | 適用場面 |
|---|---|---|
| Amazon S3 | 従量課金、高い信頼性 | 大容量サイト、企業利用 |
| OneDrive | Microsoft製品との連携 | Office365ユーザー |
| Google Cloud | 高速・大容量対応 | 高トラフィックサイト |
| FTP/SFTP | 自社サーバーに保存 | 完全にプライベートな環境 |
Amazon S3を選ぶ場合、AWSアカウントの作成とS3バケットの設定が必要です。初心者には少し複雑ですが、月額数十円から利用でき、容量制限がないのが魅力です。
実は、複数のクラウドサービスを同時に設定することも可能です。これにより、さらに安全性を高めることができますが、管理が複雑になるというデメリットもあります。まずは一つのサービスから始めて、慣れてきたら追加を検討してみてくださいね。
自動バックアップでもう安心!スケジュール設定のコツ
1. 毎日?毎週?最適な頻度の決め方
自動バックアップの頻度は、サイトの更新頻度によって決めるのがコツです。毎日記事を投稿するブログなら日次、週1回程度の更新なら週次が適切でしょう。
UpdraftPlusでは、ファイルとデータベースの頻度を別々に設定できます:
| 更新頻度 | データベース | ファイル |
|---|---|---|
| 毎日更新 | 日次 | 週次 |
| 週数回更新 | 日次 | 週次 |
| 週1回更新 | 週次 | 2週間ごと |
| 月数回更新 | 週次 | 月次 |
データベースには記事やコメントが含まれるため、頻繁にバックアップした方が安全です。一方、ファイル(テーマ、プラグイン、画像)は、そう頻繁には変更されないので、週次程度でも十分なことが多いんです。
ただし、頻度を上げすぎると、クラウドの容量をすぐに消費してしまいます。無料版を使う場合は、保存する世代数も考慮して頻度を決めましょう。
2. ファイルとデータベースを別々に設定する理由
なぜファイルとデータベースを分けるのか、疑問に思いませんか。実は、これには合理的な理由があります。
データベースは容量が小さく(通常数MB〜数十MB)、毎日バックアップしてもクラウド容量への影響は軽微です。しかし、画像や動画を多く含むファイルは数GB〜数十GBになることもあり、毎日バックアップすると容量を圧迫します。
さらに、復元の際も別々の方が便利です。記事を誤って削除した場合はデータベースのみ復元すれば済みますし、プラグインで不具合が起きた場合はファイルのみ復元できます。
設定画面では以下のように指定します:
- データベース:「毎日」
- ファイル:「毎週」
- 保存する世代数:データベース7個、ファイル4個
この設定なら、過去1週間の記事変更と過去1ヶ月のファイル変更に対応できます。
3. 古いバックアップを自動削除する設定方法
クラウドの容量制限を考えると、古いバックアップの自動削除は必須機能です。UpdraftPlusの「保持」設定で、世代数を指定できます。
推奨設定例:
| バックアップ頻度 | 推奨保持数 | 理由 |
|---|---|---|
| 毎日実行 | 7世代 | 1週間分をカバー |
| 週1回実行 | 4世代 | 1ヶ月分をカバー |
| 月1回実行 | 6世代 | 半年分をカバー |
たとえば、データベースを毎日バックアップして7世代保持する設定にすると、常に過去7日分のバックアップが保存されます。8日前のバックアップは自動的に削除されるので、容量を一定に保てるんです。
ここで注意したいのは、保持数を少なくしすぎないことです。「2世代」など極端に少ないと、問題に気づくのが遅れた場合に対応できません。最低でも1週間分は保持することをおすすめします。
いざという時に役立つ!復元の方法とポイント
1. バックアップ一覧から選んで復元する基本手順
復元作業は、バックアップよりも慎重に行う必要があります。まず、「既存のバックアップ」セクションで復元したいバックアップを確認しましょう。
基本的な復元手順:
- 復元前に現在の状態をバックアップ(安全のため)
- 「既存のバックアップ」から該当日時を選択
- 「復元」ボタンをクリック
- 復元する要素を選択(データベース、プラグインなど)
- 「復元を開始」で実行
復元中はサイトにアクセスできなくなりますが、通常は5〜10分程度で完了します。復元が完了したら、サイトが正常に表示されるか、管理画面にログインできるかを確認してください。
実は、復元に失敗することもあります。その場合でも、元のデータが消えるわけではないので、再度復元を試したり、別の日時のバックアップを使ったりできます。焦らず対処することが大切ですね。
2. 部分的な復元でピンポイント修復
UpdraftPlusの便利な機能の一つが、部分復元です。サイト全体ではなく、特定の要素だけを復元できるんです。
部分復元の例:
- プラグインのみ:新しいプラグインで不具合が発生した場合
- テーマのみ:テーマのカスタマイズでデザインが崩れた場合
- データベースのみ:記事やコメントを誤って削除した場合
- アップロードのみ:画像ファイルに問題がある場合
この機能は、問題の原因が特定できている場合に特に有効です。たとえば、プラグインの更新後にサイトが表示されなくなった場合、プラグインフォルダだけを復元すれば、記事データはそのまま残せます。
ただし、部分復元でも相互に影響する要素があります。データベースとプラグインは連携していることが多いので、どちらか一方だけを復元すると不整合が起きる可能性があります。迷った場合は、関連する要素をまとめて復元する方が安全ですよ。
3. 復元前に確認しておきたい注意点
復元は「元に戻せない」操作なので、実行前の確認が重要です。特に以下の点をチェックしてください。
復元前チェックリスト:
- 復元対象のバックアップ日時は正しいか
- 現在のサイト状態をバックアップ済みか
- 復元する要素の選択に間違いはないか
- サイトへのアクセス状況(メンテナンス時間の選択)
また、WordPressのバージョンにも注意が必要です。古いバックアップを復元すると、WordPressのバージョンも古くなる可能性があります。セキュリティ上のリスクがあるため、復元後は速やかにWordPressとプラグインを最新版に更新しましょう。
復元作業は、できれば訪問者が少ない時間帯(深夜や早朝)に行うことをおすすめします。復元中はサイトが表示されないため、ユーザビリティに影響するからです。
他のプラグインと何が違う?UpdraftPlusの魅力
1. BackWPupとの使いやすさ比較
WordPress用バックアッププラグインの中でも、BackWPupとUpdraftPlusは双璧です。両者を比較してみましょう。
| 項目 | UpdraftPlus | BackWPup |
|---|---|---|
| 復元機能 | 管理画面から直接実行 | FTP等での手動作業が必要 |
| クラウド連携 | ワンクリックで設定 | 設定項目が多く複雑 |
| 日本語化 | 一部日本語対応 | 完全日本語化 |
| 部分復元 | 対応 | 非対応 |
| 無料版機能 | 充実している | 制限が多い |
BackWPupは設定の自由度が高い反面、初心者には複雑すぎる印象があります。復元も、ダウンロードしたファイルを手動でアップロードする必要があり、トラブル時に対応が困難です。
一方、UpdraftPlusは「シンプルで確実」を重視した設計になっています。特に復元作業の簡単さは圧倒的で、WordPress管理画面だけで完結するのは大きな魅力ですね。
2. 無料版でもここまでできる機能の豊富さ
UpdraftPlusの無料版は、かなり充実した機能を提供しています。他のプラグインでは有料版でしか使えない機能も、無料で利用できることが多いんです。
無料版で利用可能な機能:
- 手動・自動バックアップ
- 主要クラウドサービス連携
- 管理画面からの簡単復元
- 部分復元対応
- スケジュール設定
- バックアップファイルの暗号化
特に注目すべきは、クラウド連携が無料で使えることです。Google DriveやDropboxとの連携は、多くのプラグインで有料機能として提供されています。
ただし、無料版にも制限があります。同時に設定できるクラウドサービスは1つまでで、より高度な機能(増分バックアップ、データベース検索・置換など)は有料版の機能です。
3. 有料版にするとさらに便利になる機能
UpdraftPlusの有料版(Premium)では、以下の追加機能が利用できます:
| 機能 | 内容 | 利用場面 |
|---|---|---|
| 増分バックアップ | 変更された部分のみバックアップ | 大容量サイト |
| 複数クラウド同時利用 | 2箇所以上に同時保存 | 高い安全性を求める場合 |
| データベース操作 | 検索・置換、修復機能 | ドメイン変更、大規模修正 |
| 自動複製 | ステージング環境作成 | 開発・テスト用 |
| プレミアムサポート | 優先的な技術サポート | 企業利用 |
特に「増分バックアップ」は、大きなサイトには有効です。初回は全体をバックアップし、2回目以降は変更された部分のみを保存するため、時間と容量を大幅に節約できます。
有料版の価格は年額70ドル(約10,000円)からです。個人ブログなら無料版で十分ですが、ビジネスサイトや大規模サイトでは、有料版の検討をおすすめします。
まとめ
UpdraftPlusは、WordPressサイトのバックアップを劇的に簡単にしてくれるプラグインです。クリック一つでサイト全体をバックアップし、クラウドサービスに自動保存できる機能は、サイト運営者の心強い味方になるでしょう。
無料版でも十分な機能があり、Google DriveやDropboxとの連携も含まれています。復元作業も管理画面だけで完結するため、万が一の際にも安心して対処できます。
バックアップは「転ばぬ先の杖」です。トラブルが起きてから準備するのではなく、今のうちにUpdraftPlusを導入して、定期的なバックアップ体制を整えておくことをおすすめします。あなたの大切なサイトを守るために、ぜひ今日から始めてみてくださいね。